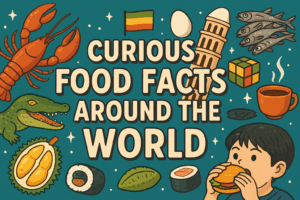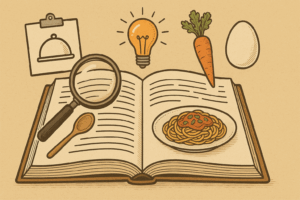パリッと香ばしい皮の中に、野菜や肉のうまみがぎゅっと詰まった「春巻き」。
食卓に登場するとちょっとうれしくなる中華の定番料理です。
でも実はこの春巻き、その名前にも由来する“季節と祝祭”の物語があるのをご存じですか?
今回は、春巻きの誕生から、世界への広がり、日本での定着までをご紹介します。
- 春巻きの起源は中国の春節に食べる行事食
- 揚げ春巻きの誕生と広東料理での普及
- 各国での呼び方やアレンジ、日本での定着まで
中国の節句料理から生まれた春巻き

春巻きの原型は、古代中国における立春や春節(旧正月)の行事食「春餅(チュンビン)」にあります。
これは小麦の薄い皮に旬の野菜を炒めた具を巻いて食べる料理で、春の訪れを祝う家庭の定番でした。
やがてその食文化が発展し、「春を包む料理」としての春巻きが広まっていきました。
揚げ春巻きの登場と普及

もともと蒸しや焼きで調理されていた春餅は、やがて油で揚げるスタイルが登場します。
とくに広東地方では、揚げ春巻きが飲茶の一品や家庭料理として人気に。
揚げることで保存性が高まり、パリパリとした食感も手伝って多くの人に親しまれるようになりました。
現在では、揚げ春巻きが世界中の中華料理の代表格として知られています。
世界への広がりと日本での春巻き

春巻きは中国からアジア各地へと伝わり、各国で独自の進化を遂げます。
たとえば、フィリピンでは「ルンピア」、ベトナムでは「チャーゾー」、さらに「生春巻き(ゴイクン)」も登場。
日本には明治時代に本格中華料理として伝わり、昭和期には家庭料理として定着。
豚肉・たけのこ・春雨など、日本の食材を活かした“和風春巻き”も人気です。
冷めても美味しいことから、お弁当や惣菜でもおなじみの存在となりました。
まとめ
春巻きは、春の喜びと季節の恵みを包み込んだ料理として、時代や国境を越えて愛されてきました。
そのシンプルな構造ゆえに、さまざまな土地の食材や文化と結びつき、今なお進化し続けています。
次に春巻きを味わうときは、そんな“物語ごと包み込んだ一皿”として、じっくり楽しんでみてはいかがでしょうか。
 ココちゃん
ココちゃん春巻きって、春のごちそうだったんだね!
おいしいだけじゃなくて、歴史も詰まってるって知ったら、もっと好きになっちゃった♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。