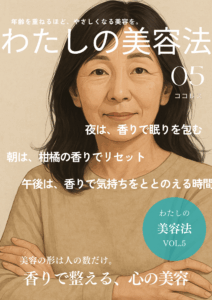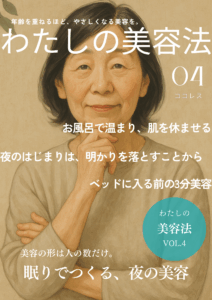風の音に耳を澄ませ、畳の香りにほっとする時間。
昔の日本には、自然と寄り添いながら毎日をていねいに過ごす知恵がありました。
日々の暮らしをととのえることは、心を静かに整えることでもあります。
この記事では、日本古来の生活に息づく「ととのえる知恵」と、現代にも取り入れやすい習慣をご紹介します。
- 自然と調和する暮らしが、心と体を整える
- 昔ながらの道具や習慣には、ムダのない美しさがある
- 季節の移ろいを感じることで、毎日が豊かになる
自然のリズムに寄り添う

昔の日本人は、自然とともに暮らしていました。朝は日の出とともに目を覚まし、夜は日が沈むと休む。
夏は風通しのよい家で涼をとり、冬は火鉢や囲炉裏で身を温める——そんな生活の中には、「あるものを活かす」工夫がたくさんありました。
便利なものが少なかった分、不便さを受け入れ、その中に心地よさを見つける力が育まれていたのかもしれませんね。
道具と習慣に宿るぬくもり

風呂敷や蚊帳、土鍋やちゃぶ台、ほうきとちりとり。昔の暮らしには、必要なものだけを大切に長く使う知恵がありました。
「ものを減らす」のではなく、「ものをいとおしむ」気持ちが根づいていたのです。
たとえば、破れたものを縫い直し、欠けた器を金継ぎして使い続ける。そんな習慣の中には、ものとの付き合い方だけでなく、自分や家族との関係も大切にする姿勢が見えてきます。
季節のある暮らしが心を満たす

春は草餅や梅の花、夏は打ち水や風鈴。秋は月見に紅葉狩り、冬は炬燵や火鉢でぬくもる時間。
こうした季節ごとの楽しみを暮らしに取り入れることで、日常がぐっと豊かになります。
また、朝のお湯沸かしや、ほうきで掃き掃除をする所作には、心を落ち着かせる力もあります。
何気ない時間の中に、静かに自分をととのえる瞬間がある——それが、和の暮らしの魅力です。
まとめ
日本古来の暮らしには、自然や季節、そして自分自身とやさしく向き合う知恵がたくさん詰まっています。
それは、便利さやスピードでは得られない、本当の心地よさなのかもしれません。
窓を開けて風を感じる、床をさっと掃く、季節の草花を一輪飾る——そんな小さなことからでも、心と空間はゆっくり整っていきます。
昔のやり方を、今の暮らしに少しだけ取り入れてみませんか?
 ココちゃん
ココちゃんちゃぶ台や蚊帳って、なんだか懐かしくてほっとするね。
季節を感じる暮らしって、心がゆるんで気持ちいいな〜。
明日の朝は、窓を開けて風を吸い込んでみようっと♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。