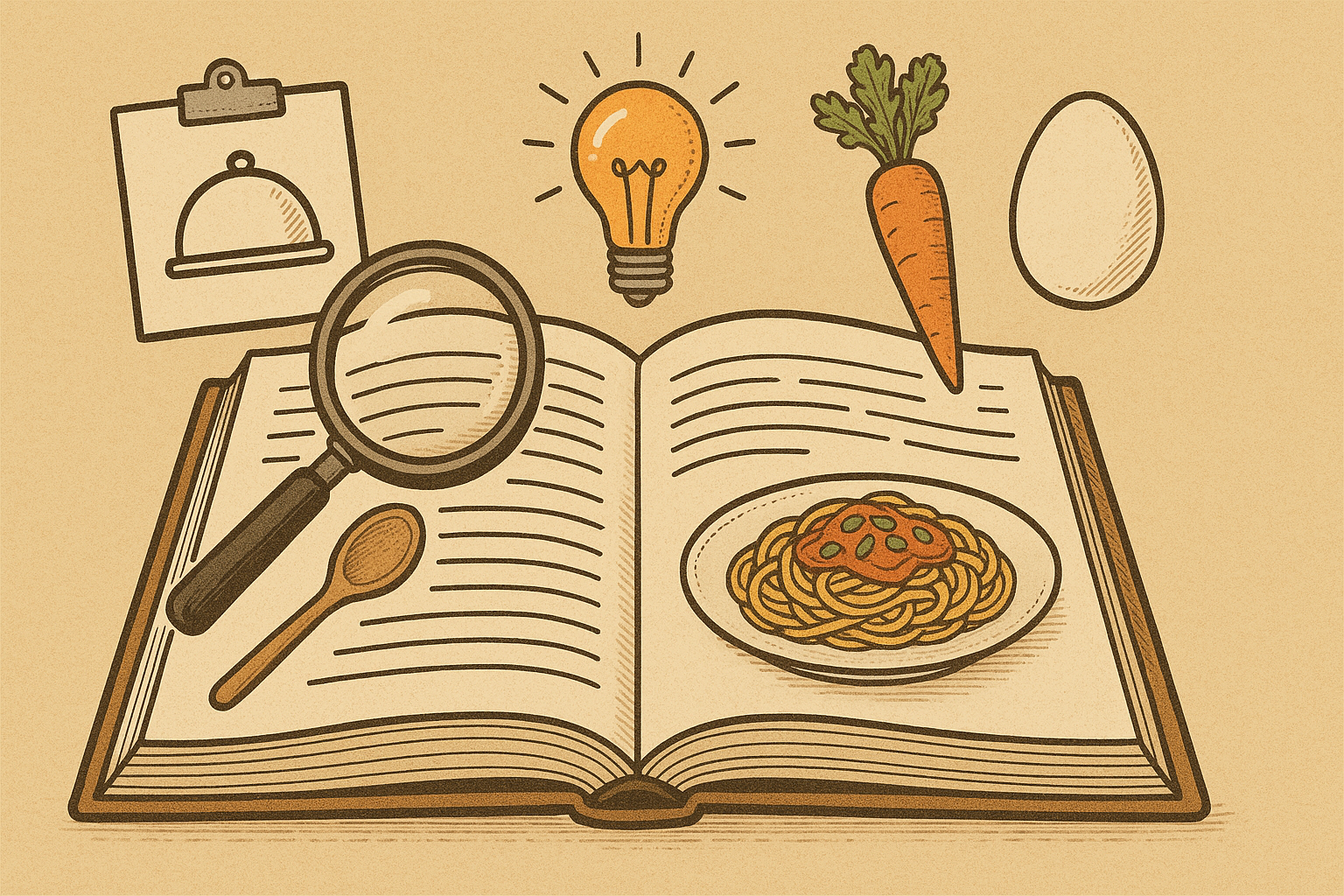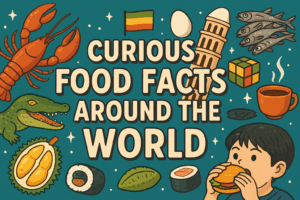毎日のごはんも、ちょっとした豆知識を知るだけでグッと面白く、そしておいしく感じられるかもしれません。
この記事では、「誰かに話したくなる!」ような料理にまつわる雑学を7つ厳選してご紹介します。
次の食事やおしゃべりの話題に、ぜひ役立ててください。
- 戦国時代のおにぎりは“丸型”だった!
- カレーやオムライスは日本で進化した“洋食”文化
- パンの耳やスプーン料理には意外な歴史がある
料理に隠された歴史の断片たち

最初の雑学は、日本人に馴染み深い「おにぎり」。実は戦国時代の武将たちが携帯食として愛用していたもので、当時は丸く握られていました。冷めても食べやすく、戦の合間に片手でパクっと食べられる実用的な食べ物だったのです。
さらに意外なのは「スパゲッティ」。フォークが登場するまでは、手づかみで食べていたという説も。上品なイタリア料理のイメージとは裏腹に、かつては庶民的な食べ方だったのですね。
進化した“洋食”と日本人の知恵
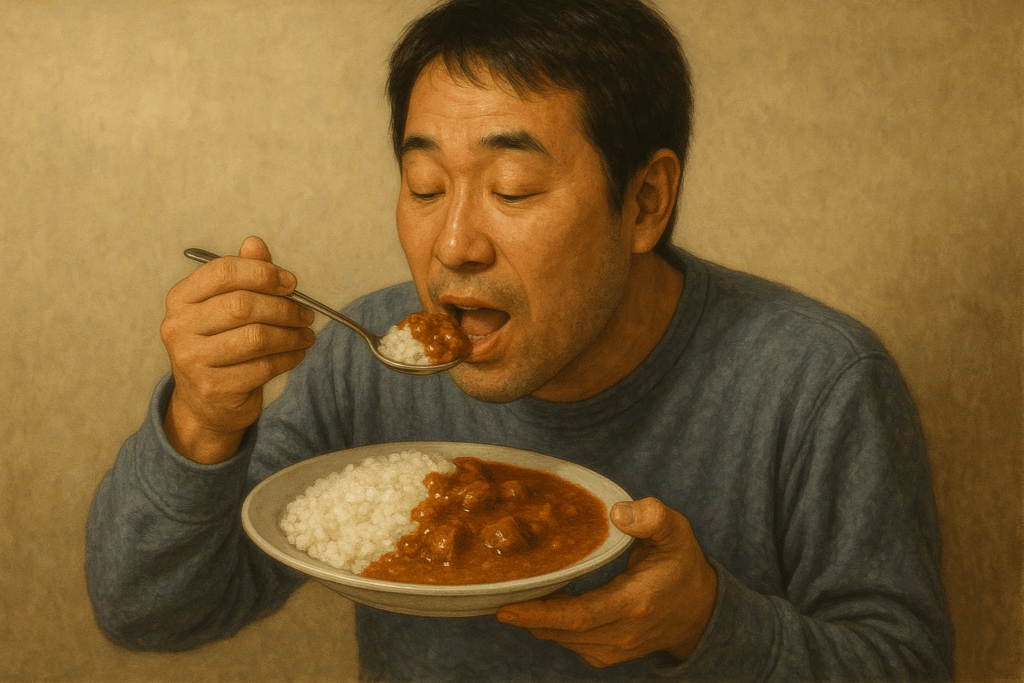
私たちの食卓で定番の「カレーライス」は、実はイギリス経由で伝わった“洋食”。インドのスパイス文化がイギリス風にアレンジされ、とろみのある日本式カレーへと変化しました。同じく日本で生まれた「オムライス」も、フランスのオムレツとは異なり、ケチャップごはんと卵を組み合わせた創作料理。
どちらも、日本人の口に合うよう工夫されて進化した“町の洋食”です。見慣れた料理にも、時代と文化の工夫が詰まっています。
シンプルなものにこそ、深い物語がある
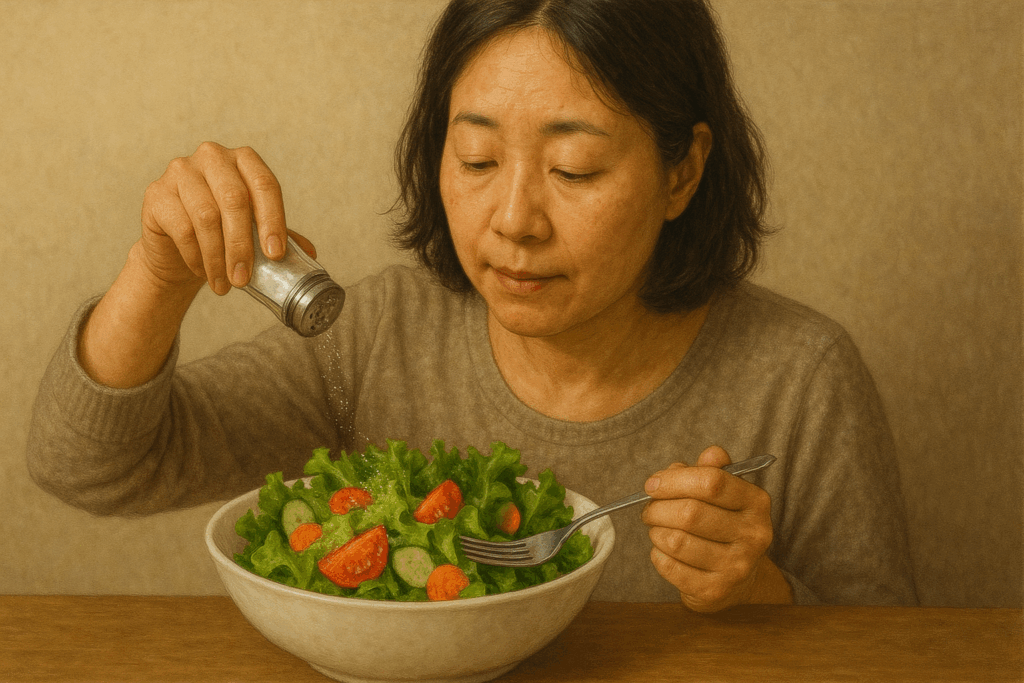
「サラダ」はラテン語の「塩(サラ)」に由来し、もともとは塩をふった野菜料理でした。現代のようにドレッシングがかかっていたわけではなく、塩だけで楽しむシンプルなものだったのです。
そして「パンの耳」。今では切り落とされがちなこの部分、かつてヨーロッパでは香ばしく歯ごたえのある“ごちそう”とされ、王侯貴族が好んで食べたといわれています。
また、「スプーンを使う料理」自体が、かつては特別なものとされていたという話も。江戸時代の日本ではスプーン自体が一般的ではなく、スープやプリンなどを食べるのは限られた人だけの贅沢だったのです。
まとめ
普段の食卓にある料理にも、驚くような背景や文化が詰まっています。
知れば知るほど、いつもの一皿がもっと味わい深く感じられる――それが食の面白さ。
次の食事では、今回の雑学を思い出しながら、身近な料理に込められた物語を感じてみてください。
 ココちゃん
ココちゃんパンの耳が“ごちそう”だったなんてビックリ!
毎日のごはんにも、小さな歴史がたくさん詰まってるんだね〜♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。