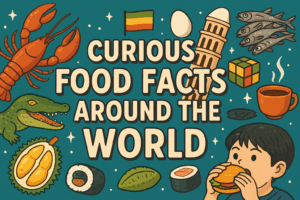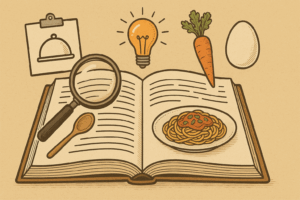牛肉や野菜をじっくり煮込んだ、滋味あふれるスープ「ポトフ」。
味はシンプルながら、どこかホッとするやさしい洋風煮込みです。
今回は、そんなポトフの起源やフランスの食文化での位置づけ、日本への伝来と家庭料理化の過程をやさしくご紹介します。
- ポトフはフランスの農民が生んだ家庭料理
- 「母の味」として今も受け継がれている
- 各国に似た煮込み料理がある
- 日本では洋風スープとして定着
ポトフの起源は中世フランスの農村料理

ポトフ(Pot-au-feu)はフランス語で「火にかけた鍋」という意味。
起源は中世のフランス。農民たちが手に入る食材を大鍋でじっくり煮込んだ料理から始まりました。
主に牛肉とにんじん、玉ねぎ、セロリ、カブなどの根菜類を煮込むシンプルな構成。
高価な材料を使わず、家庭の台所で育まれた“素朴なごちそう”です。
フランス家庭に根づく「母の味」

フランスでは日曜日に家族で囲む料理や、母の味としてポトフが親しまれています。
地域や家庭によって使う肉や野菜、スパイスもさまざま。
たとえば鶏肉やソーセージを使ったり、マスタードを添えたり、パンと一緒に食べたりと自由自在。
残ったスープはリゾットや他の煮込みにリメイクされることも多く、無駄のない知恵が息づいています。
世界と日本に広がるポトフ

ドイツではアイスバイン、イタリアではボッリート・ミストと呼ばれる類似の煮込み料理があり、ヨーロッパ各地に同じ調理文化が根づいています。
日本では明治時代にフランス料理として紹介され、戦後には洋食文化とともに「洋風おでん」や「肉じゃが」に近い家庭料理として定着。
コンソメやブイヨンを使った、より和風にアレンジされたポトフも普及しています。
まとめ
ポトフは、フランスの家庭で何世代にもわたり受け継がれてきた、やさしさと知恵に満ちた煮込み料理です。
体を温め、心を満たす料理として、現代でも季節を問わず楽しめる一品。
今日の食卓に、ひと鍋で満たされる“フランスのぬくもり”を加えてみてはいかがでしょうか?
 ココちゃん
ココちゃんポトフって、やさしい味と香りで心まであったかくなるね!
野菜もたっぷりで、からだにもうれしい一皿♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。