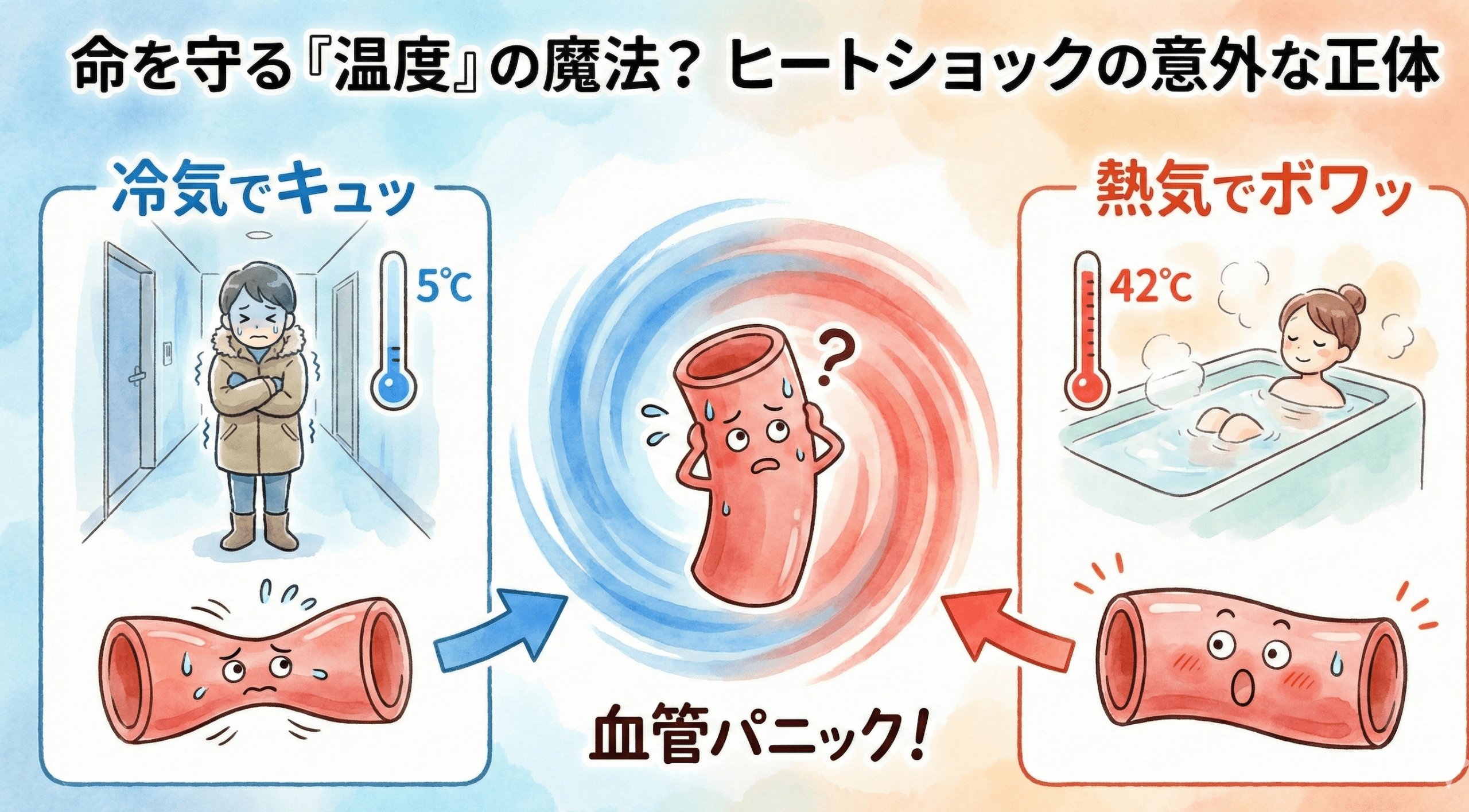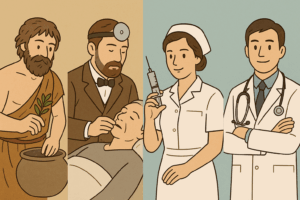「夜中に体調が悪くなった…でも、救急車を呼ぶほどじゃないかも?」
そんなとき、“どこに相談すればいいか”を知っているだけで、落ち着いて対応することができます。
この記事では、高齢者やそのご家族が、緊急時に頼れる医療・相談窓口や日常的な備えについて、わかりやすくご紹介します。
- 緊急相談窓口「#7119」や各自治体の救急相談で、迷ったときに判断できる
- 夜間・休日の医療機関は「医療情報ネット」で事前に確認を
- 心の不調や孤独には、専門の電話相談が活用できる
- 緊急連絡先や情報は「見える場所」に用意しておくことが重要
迷ったときの相談窓口を知っておく

突然の体調不良で「救急車を呼ぶべきかどうか」迷ったら、救急安心センター「#7119」が頼りになります。
医師や看護師が24時間対応しており、自宅で様子を見るか、受診が必要か、救急搬送かを判断する手助けをしてくれます。
ただし、対応地域は限られているため、非対応地域では自治体ごとの「救急電話相談窓口」を確認しましょう。
「とりあえず相談する」という行動が、命を守る第一歩です。
夜間や休日の医療機関を探すには

夜間や休日に診療可能な病院を探すには、各自治体の「医療情報ネット」や「○○県 夜間診療」などのキーワード検索が便利です。
たとえば東京都では「ひまわり」サービスが、地域の対応病院を一覧で表示してくれます。
最寄りの夜間救急センターや輪番病院は、スマホのブックマークや紙にメモして冷蔵庫に貼っておくと安心です。
突然のときに慌てないために、事前の情報チェックと備えが大切です。
心の不安にも「相談の窓口」を

緊急時の不安は、体の症状だけではありません。
孤独感や気分の落ち込みなど、心の緊急時にも相談できる窓口があります。
たとえば、「いのちの電話」や各自治体が設置している「心の健康電話相談」。
また、介護者向けのストレス相談や、認知症の不安に対応する相談窓口も活用できます。
「こんなことで相談していいのかな…」と思わず、まずは声を届けてみることが大切です。
まとめ
救急時に“誰に連絡すればよいか”を把握しておくことで、迷いの時間を減らし、命を守る行動ができます。
連絡先一覧や持病・服薬情報などを見える場所にまとめておくことも、安心につながる準備のひとつです。
📌 今すぐ「緊急メモ」を1枚、冷蔵庫や電話のそばに貼っておきましょう。
 ココちゃん
ココちゃん緊急時の連絡先、私も冷蔵庫にメモを貼ったよ!
備えがあれば、もっと安心だね〜


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。