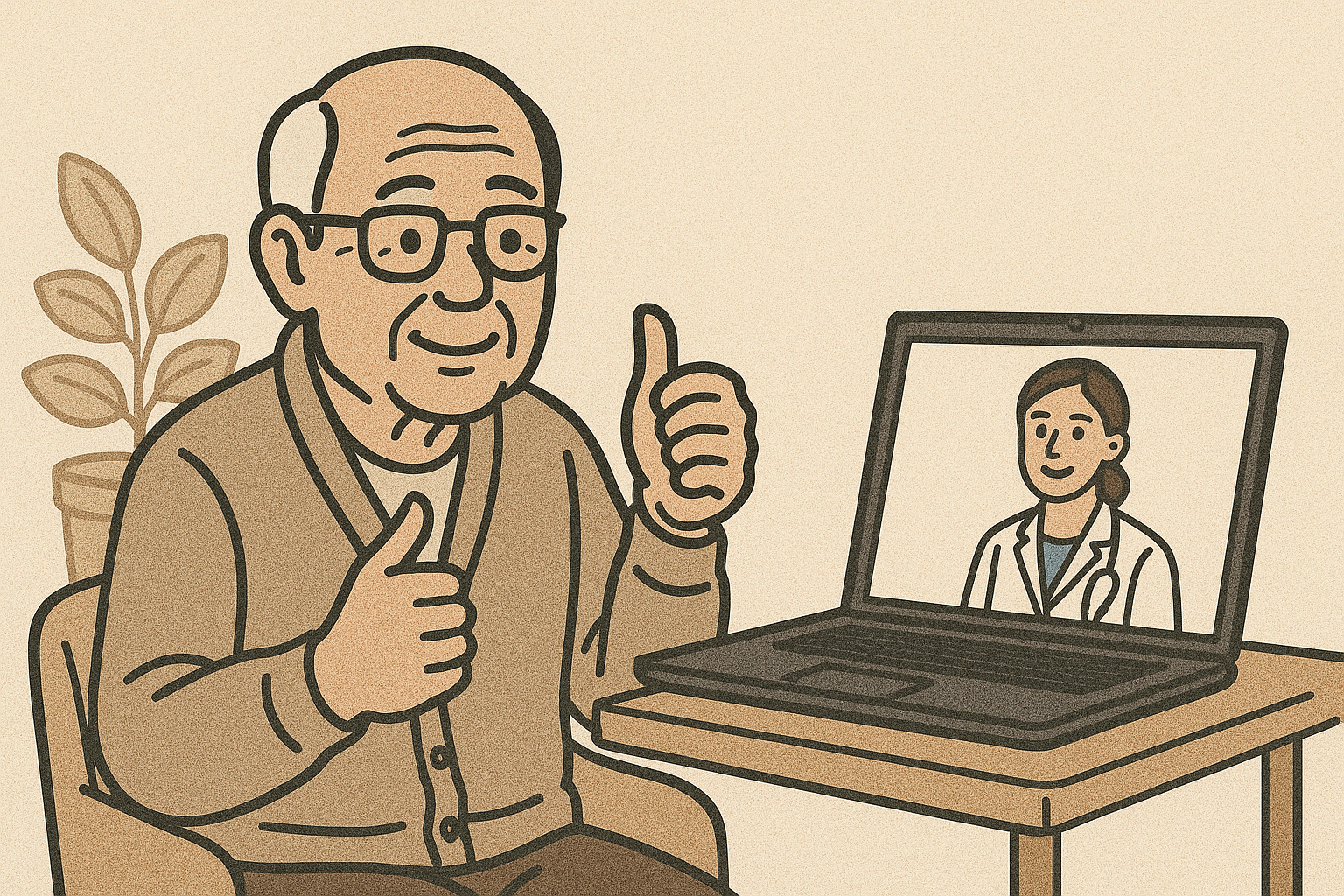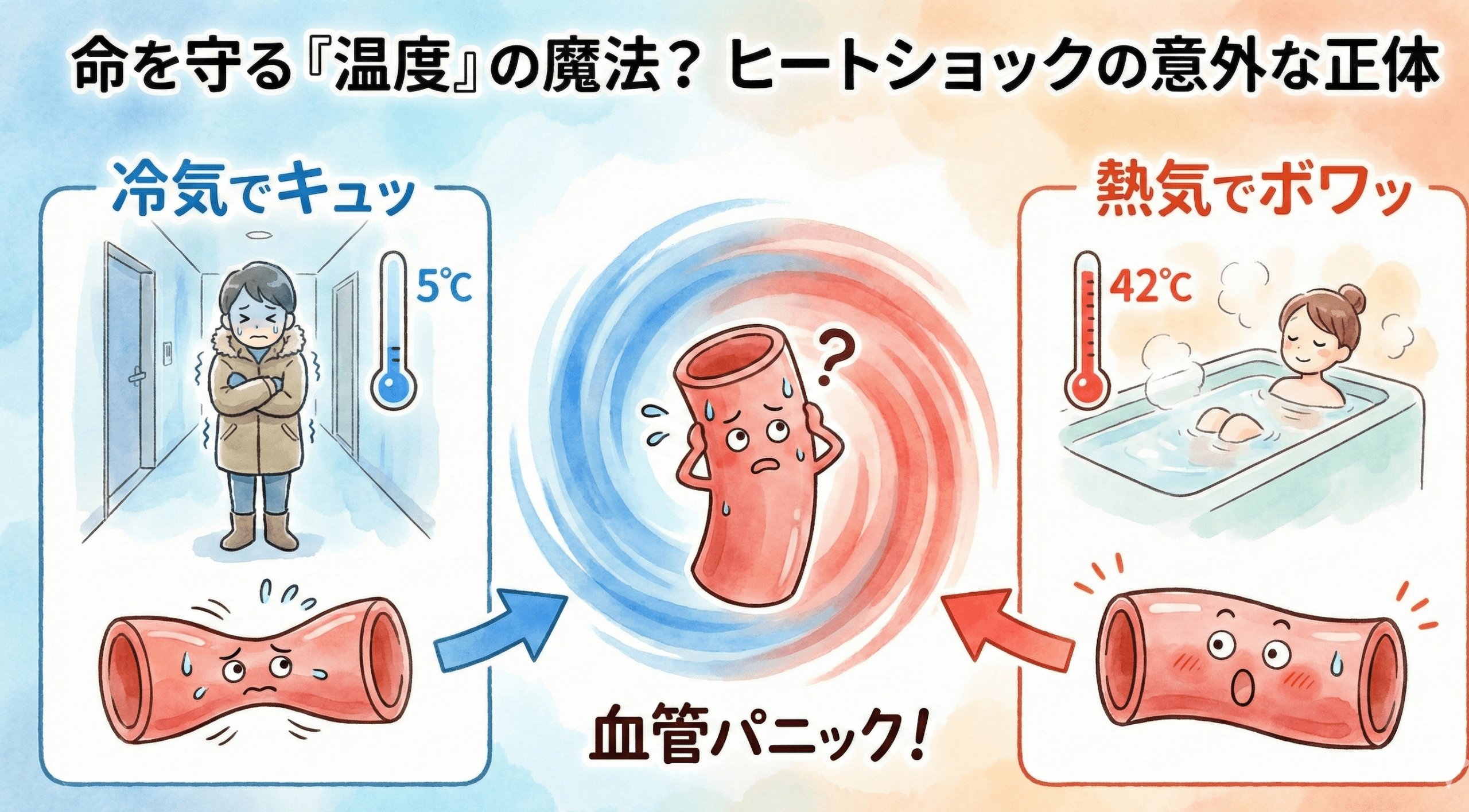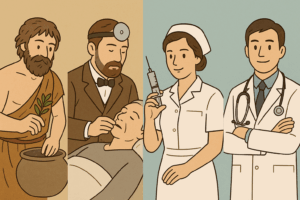高齢になったり、病気が長引いたりすると、「もう病院に通うのが大変…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに頼りになるのが、医師や看護師が自宅を訪問して診療やケアを行う「在宅医療制度」です。
この記事では、在宅医療のしくみや対象となる人、利用の流れや費用の目安について、わかりやすくご紹介します。
- 在宅医療は「通えない人のための訪問診療制度」
- 対象者や利用方法は多くの人に開かれている
- 費用負担も保険適用で安心して利用できる
在宅医療ってどんな制度?
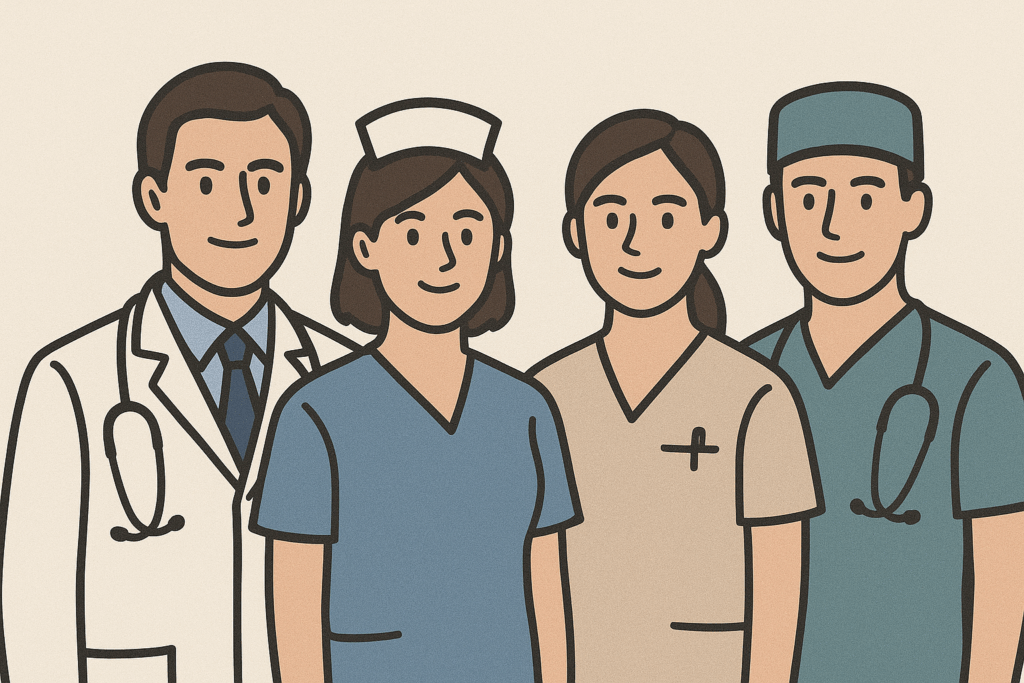
在宅医療とは、自宅にいながら診察や治療を受けられる制度です。
医師の「訪問診療」だけでなく、看護師の「訪問看護」、薬剤師による薬の管理、リハビリスタッフの支援など、複数の専門職が連携して支えるのが大きな特徴です。
通院が難しい人でも、住み慣れた家で安心して療養できるようサポートする医療体制が整っており、緊急時の連絡先や24時間対応の病院も増えています。
どんな人が、どうやって使えるの?

在宅医療の対象となるのは、たとえば以下のような方です。
- 寝たきりや体が不自由で通院が難しい高齢者
- がんなどで自宅での療養・看取りを希望している人
- 認知症で外出が不安な人
- 医療機器(酸素、胃ろうなど)を使用している人
利用したいときは、まずかかりつけ医や地域包括支援センターに相談してみましょう。紹介を受けた後は、訪問診療医との契約・初回訪問を経て、定期診療がスタートします。相談は早めが安心です。
費用や相談先は?
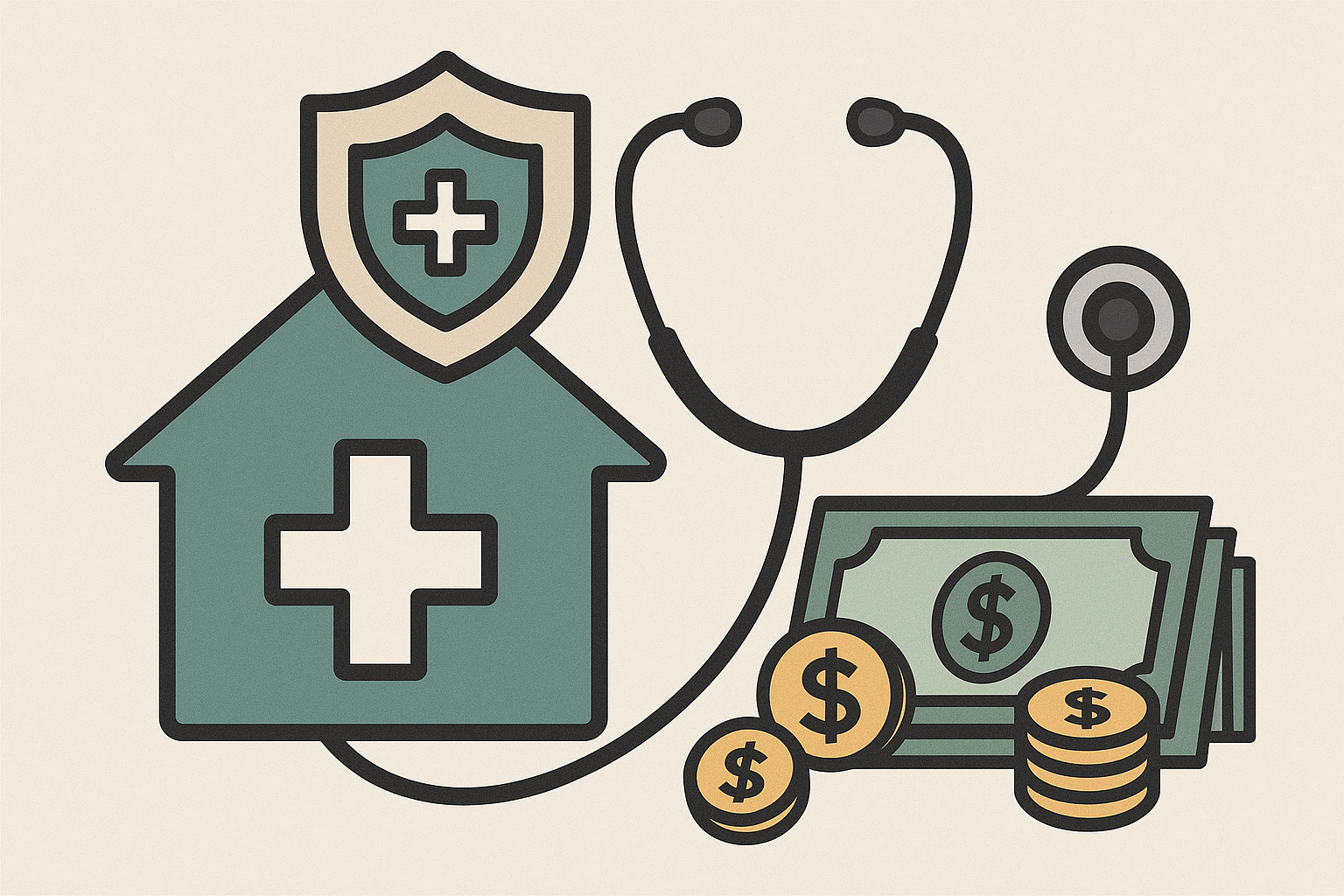
在宅医療は健康保険や介護保険が適用されるため、自己負担は比較的抑えられます。
1回の訪問診療での自己負担は約500〜1,500円(1〜3割負担)、訪問看護やリハビリも介護保険の範囲内で利用可能です。
また、高額療養費制度を活用すれば、負担が一定額を超えた場合に補助を受けられるので安心です。
相談先は、かかりつけ医、地域包括支援センター、市町村の介護保険課など。在宅医療連携拠点が設置されている地域もあります。
まとめ
在宅医療制度は、「通えなくなったから仕方ない」というものではなく、「自宅で安心して過ごすための前向きな選択肢」です。
医療の形が変化する今、住み慣れた場所で療養したいという想いを、制度がしっかり支えてくれます。
元気なうちから情報を知っておくことで、将来の備えにもなります。
家で暮らすことを大切にしたい方にとって、在宅医療は心強い存在となるでしょう。
 ココちゃん
ココちゃん病院じゃなくて、家で診てもらえるなんて心強いね!
早めに相談しておくのが安心への第一歩だね〜♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。