何気なく「使っている」道具や言葉、習慣。
でもその“使い方”には、実は長い歴史やおもしろい工夫が隠れていることもあります。
この記事では、「使う」という行為にまつわる、思わず誰かに話したくなる雑学を5つご紹介します。
暮らしを見つめ直すヒントとして、身近なものを楽しく眺めてみましょう。
- お箸の起源は「食べる」より「神事」
- ボールペン1本で小説が1本書ける?
- 塩は“調味料”だけでなく“清め”の道具
- スマホは“道具の集大成”とも言える存在
- 「使う」の語源は“人に仕える”だった
お箸は最初「食べる道具」ではなかった?
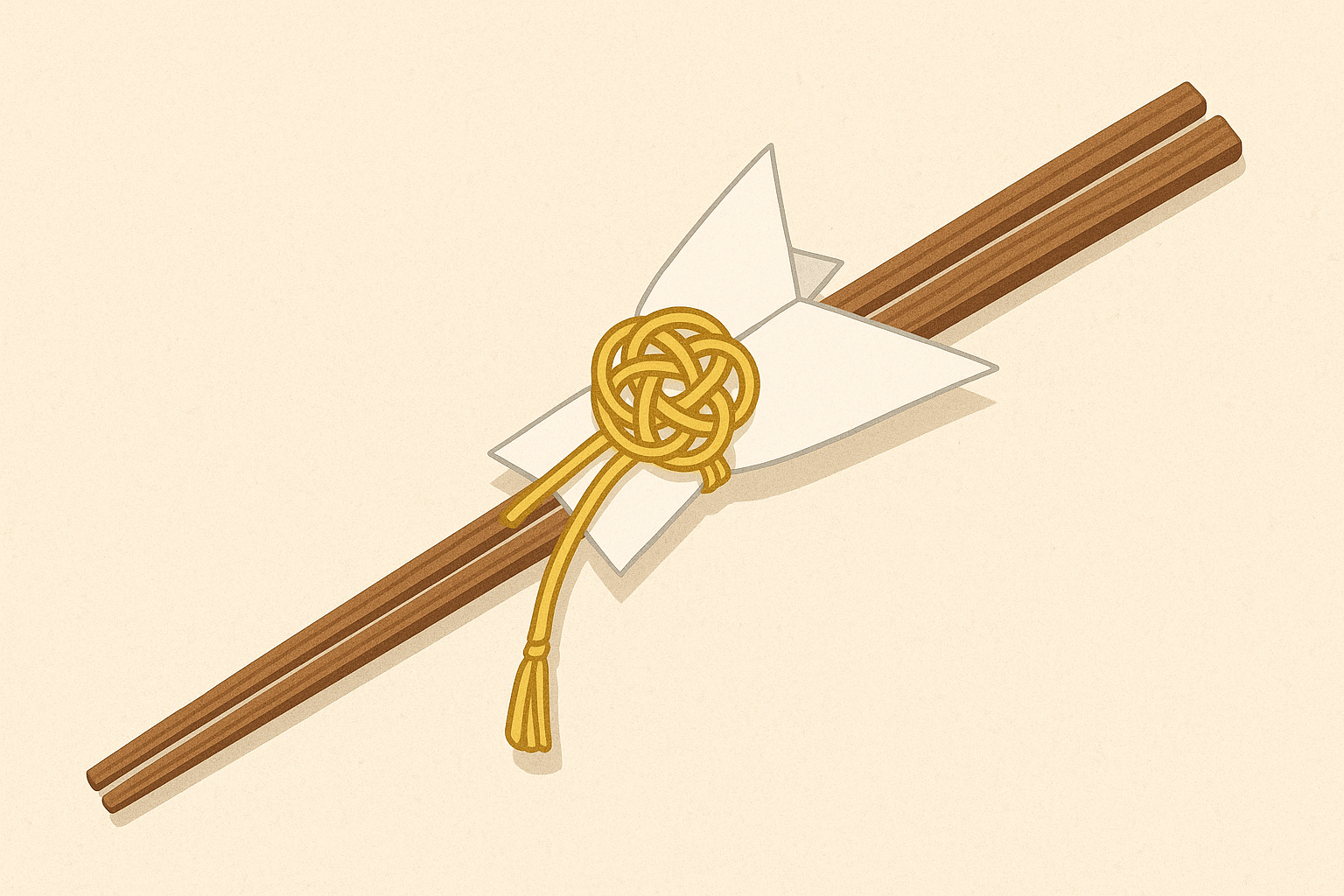
毎日何気なく使っているお箸ですが、その起源は古代中国にまでさかのぼります。
実は、最初は“食べるため”ではなく、「火の神に触れないように料理をつかむ」という神聖な用途だったそうです。
特に神事の場では、素手で料理に触れないための道具として重要な役割を果たしていました。
日本で広く使われるようになったのは奈良時代以降。初期の箸は竹製で、ピンセットのような形だったという説もあります。
「食べる」ための道具としての発展には、文化とともに人の知恵が積み重ねられているのです。
ペン1本にこめられた“書く力”

普段使っているボールペン、実は1本で書ける文字数をご存じですか?
一般的には、およそ1万~1万5千文字とされており、これは原稿用紙でいうと約25~40枚分。
つまり、短編小説1本がまるごと書けるほどの情報量を、1本の小さな道具が支えているのです。
書く道具としての“ボールペン”もまた、便利さと共に人の知的活動を支える存在といえるでしょう。
塩は「清め道具」としても使われてきた
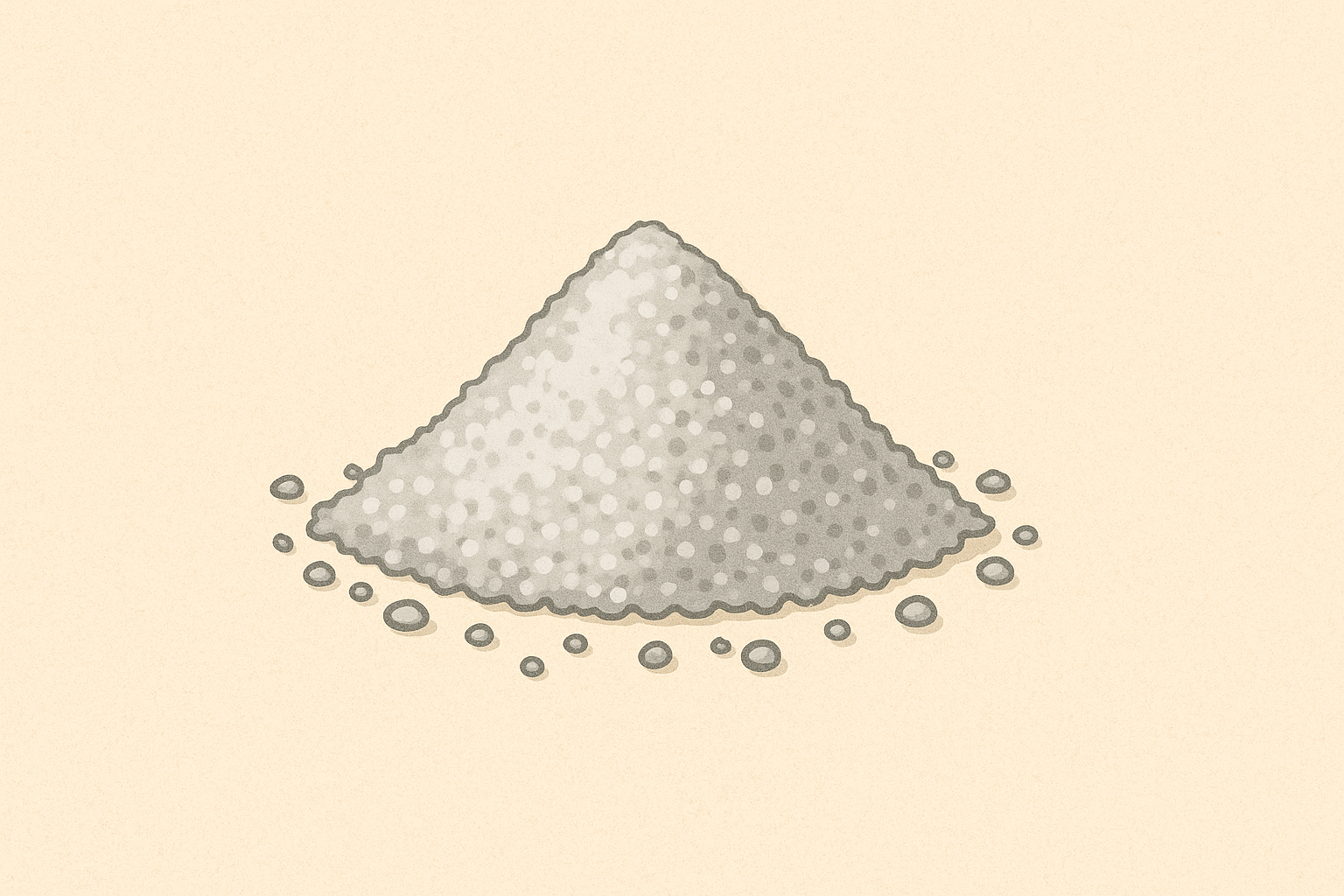
塩といえば料理に欠かせない調味料ですが、古くから日本では「清め」の力があると考えられてきました。
たとえば、
・相撲の土俵でまく「清め塩」
・お葬式後に手渡される「清め塩」
・家の四隅や玄関に置かれる「盛り塩」
こうした使い方には、“場を整える”道具としての意味が込められています。
現代でもお店や旅館の玄関先などで見かけることがありますよね。
まとめ
「使う」という行為には、単なる操作以上の意味が込められています。
道具や言葉には、時代や文化の背景、そして人間の知恵がぎゅっと詰まっているのです。
身の回りのものに目を向けてみると、当たり前に“使っている”ものの奥に、新たな発見があるかもしれません。
💡 使うとは、伝えること。つなぐこと。そして、文化を守ること。
そんなふうに思えてくると、日常が少し楽しくなりますね。
 ココちゃん
ココちゃん『使う』って、ただの動作じゃないんだね! 昔からの知恵がぎゅっとつまってるって知って、ちょっと感動しちゃった♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。




