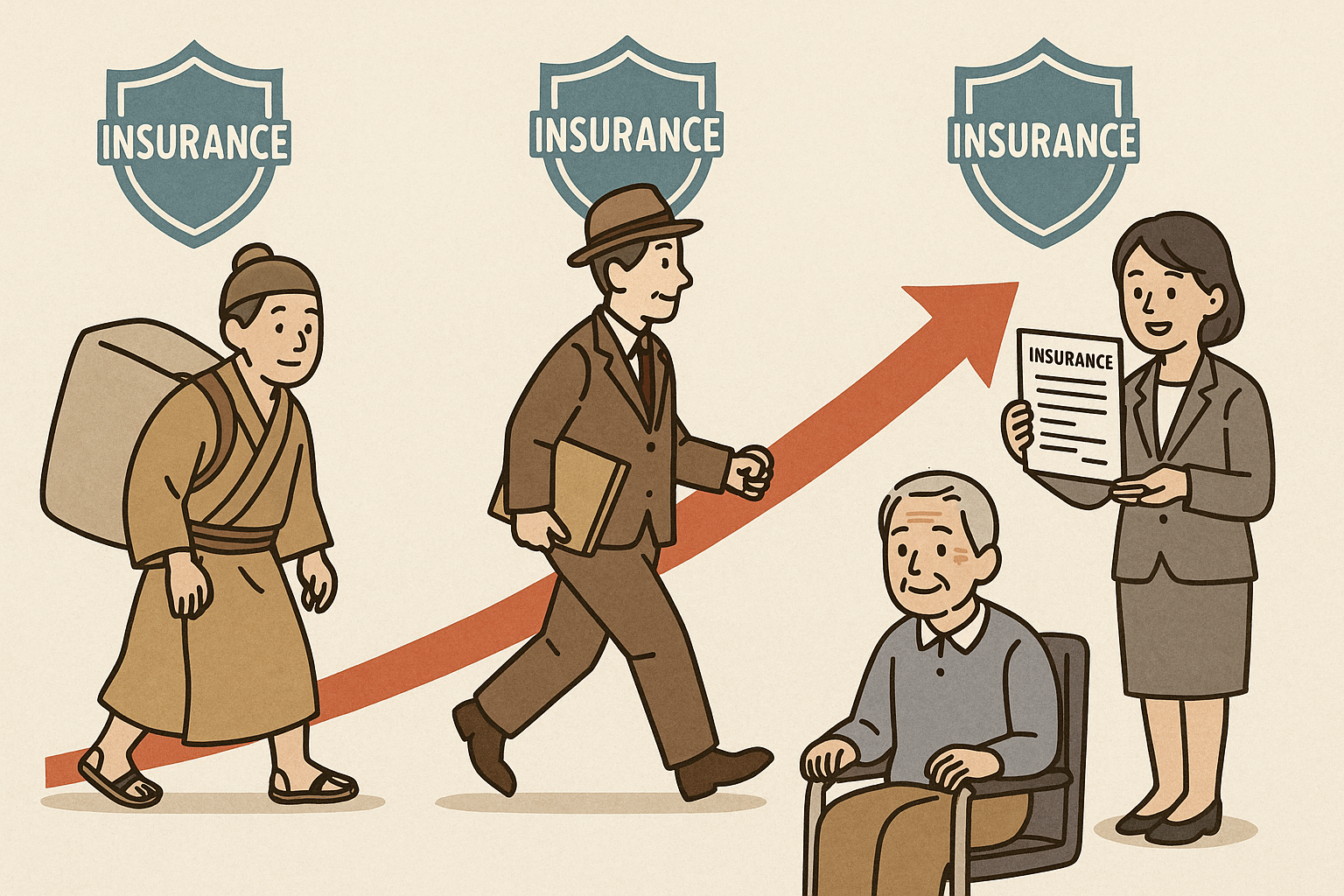病気やけが、事故や災害——
「もしも」に備える仕組みとして、私たちの暮らしに深く根づいている保険。
いまでは当たり前にあるこの制度も、もともとは人と人との“助け合い”から生まれたものでした。
この記事では、保険のはじまりから現在の公的制度にいたるまでの歴史を、やさしく振り返ります。
- 保険の起源は古代の「相互扶助」の考え方から
- 大航海時代に海上保険が登場し、近代的制度へと発展
- 国民皆保険など、公的制度として社会に根づく
- 高齢社会やデジタル化に合わせて保険も進化中
保険のはじまりは“助け合い”の精神から
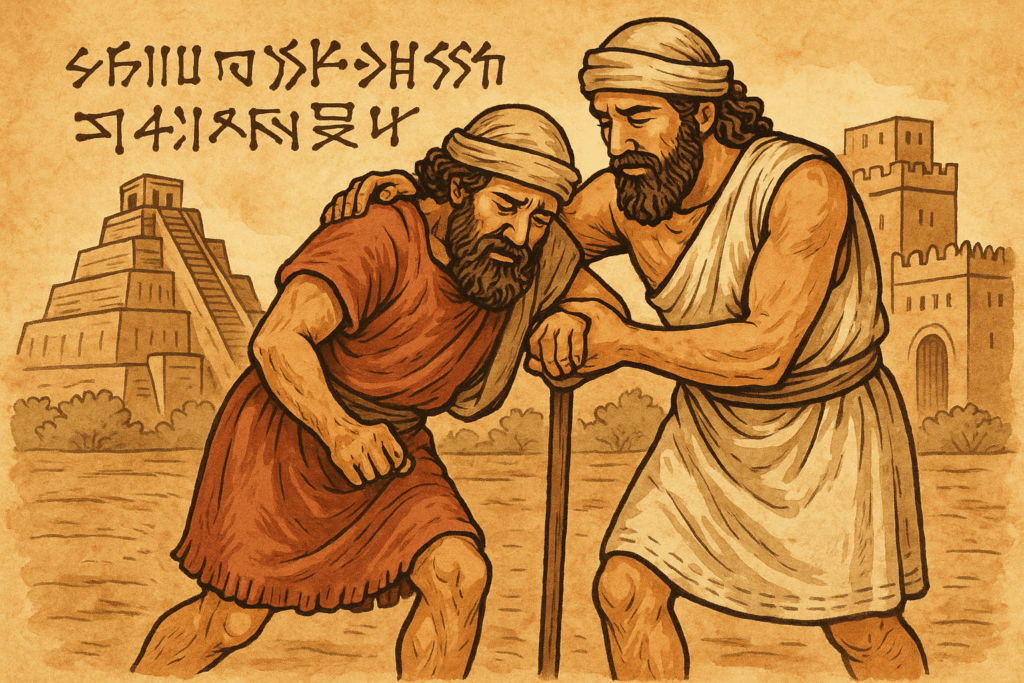
保険の原型は、古代から存在していた「相互扶助(そうごふじょ)」という考え方にあります。
たとえば、バビロニアや古代ローマでは、商人たちが船の沈没に備えて、互いに損失を補い合うような仕組みを持っていました。
中世ヨーロッパでは、職人の組合であるギルドが、災害やけがの際にお金を出し合う制度を運用していました。
保険の始まりは、困ったときはお互いさまという、暮らしの中のやさしい知恵だったのです。
海のリスクが生んだ「海上保険」
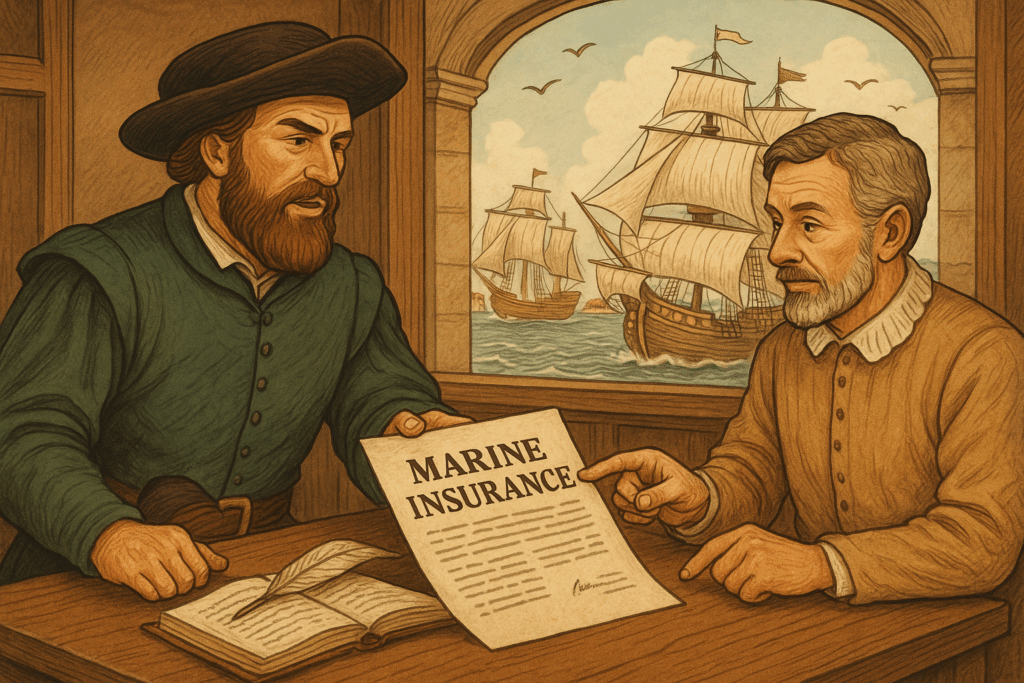
14世紀から17世紀にかけての大航海時代、長く危険な航海に出る商人たちの間で、「海上保険」という考え方が広まりました。
貨物や船が損傷したときの経済的損失をカバーするために、複数の出資者が補償金を提供する仕組みが生まれたのです。
1688年には、イギリス・ロンドンのコーヒーハウスで「ロイズ保険組合」が誕生し、ここから近代的な保険制度の原型が確立されました。
その後、火災保険や生命保険などさまざまな保険が登場し、保険は「ビジネスとしての仕組み」へと広がっていきました。
社会全体で支える“公的保険”の登場
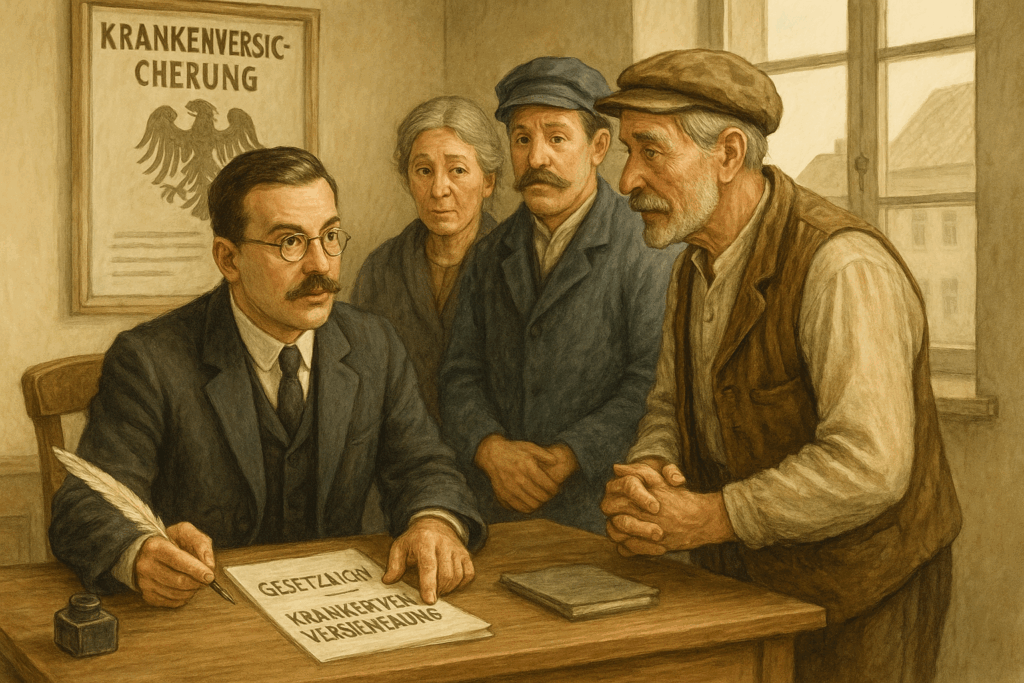
19世紀末、ドイツではじめて国家による社会保険制度が導入されました。
首相ビスマルクのもと、「病気や事故は国全体で支えるべき」という思想から「疾病保険」が整備されます。
日本では1922年に健康保険法が制定され、1938年から被用者向けに制度がスタート。
そして1961年、「国民皆保険制度」が実現し、すべての国民が医療保険に加入する社会がつくられました。
これにより、誰もが安心して医療を受けられる時代が到来したのです。
まとめ
保険は、もともと「困ったときに助け合う」という人間の本質的な思いやりから始まりました。
時代が進む中で、制度として形を整えながら、私たちの暮らしの中にしっかりと根づいていったのです。
今では、公的な医療保険や介護保険、年金制度のほかに、民間の保険会社が提供する補償も身近になりました。
保険は、未来の安心を支える“見えない準備”。
自分や家族の生活を守るために、これからも大切に向き合いたい仕組みです。
 ココちゃん
ココちゃん保険のはじまりが“助け合い”だったなんて、ちょっと感動しちゃった!
ずっと続いてきた“安心のバトン”なんだね♪


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。