「年金だけで足りるかな?」「急な出費が心配…」
年齢を重ねるにつれ、お金に関する不安は少しずつ大きくなります。
でも、大切なのは“ムリなく・安心して”管理できる方法を知っておくこと。
この記事では、高齢期の暮らしに合ったお金とのつきあい方や、今からできる準備についてやさしく紹介します。
- 「見える化」でお金の不安を軽減
- 使い道別に分ける“3つのお財布”管理
- 使える制度は積極的に活用しよう
- 詐欺・トラブルから資産を守る備えも必要
まずは“見える化”から始めよう

お金の不安は、「よく分からない」ことから生まれます。
まずは、自分が毎月どのくらい使っているかをざっくり把握してみましょう。
家計簿アプリやノート、カレンダーの余白でも大丈夫です。
「食費」「医療費」「光熱費」「趣味・娯楽費」など、いくつかの項目に分けると見やすくなります。
月の終わりに「今月はどうだったか?」を振り返る習慣をつけると、不安が“数字”として見えてきます。
書き出すことで、「何にどれだけ使えるか」の判断もしやすくなります。
“3つのお財布”で管理する

お金の使い方をシンプルに整えるには、「使い道ごとに分ける」ことがポイントです。
おすすめは、以下のような“3つのお財布”方式。
| お財布の種類 | 使い道 |
| 日常用 | 食費・水道光熱費などの生活費 |
| 予備用 | 医療費・冠婚葬祭などの突発的出費 |
| 楽しみ用 | 趣味や外出、小さなごほうびなど |
この方法だと、「使いすぎたかな?」という不安も減り、心のゆとりが生まれます。
節約ばかりを意識するのではなく、「安心して使えるお金」も確保することで、暮らしに彩りが戻ってきます。
制度を活用し、お金を“守る”
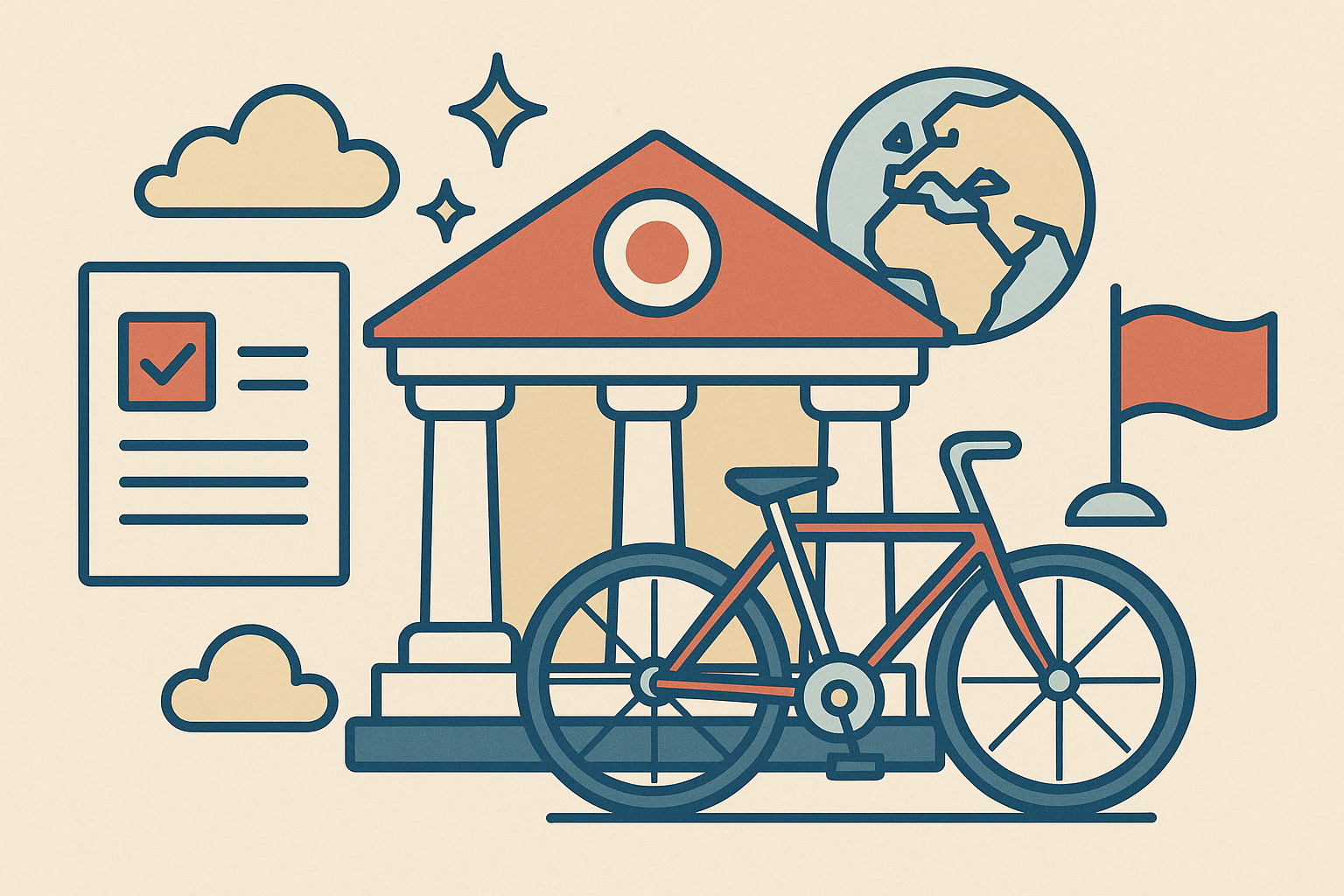
公的な支援制度や助成金を活用することも、賢いお金の整え方のひとつです。
たとえば:
高額療養費制度(医療費が一定額を超えた際に払い戻し)
各種手当・減免制度(障害手帳、固定資産税減免など)
地域の生活支援給付や家計相談窓口
お住まいの自治体で利用できる制度は異なりますが、「何か使えるかも」と思ったら、まずは地域包括支援センターや市役所に相談してみましょう。
また、詐欺や悪質な勧誘からお金を守る意識も大切です。
見知らぬ電話・メールへの対応は慎重にし、通帳やカードの管理は信頼できる家族と共有しておくと安心です。
まとめ
お金との向き合い方は、年齢とともに「増やす」から「守る・活かす」へと変わっていきます。
大切なのは、自分らしく安心できる方法を選ぶこと。
「使っていいお金」「とっておくお金」「楽しむお金」――この3つのバランスを整えることで、日々の暮らしがより前向きで自由になります。
お金は我慢するものではなく、暮らしを支える味方として活かしていきましょう。
 ココちゃん
ココちゃんお金のこと、なんとなく不安だったけど、「ちょっとずつ整える」でいいんだね。わたしも“楽しみ用のお財布”つくってみようっと!


作成者:ココレス編集部
*写真はイメージです。
ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。
脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。
「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。




